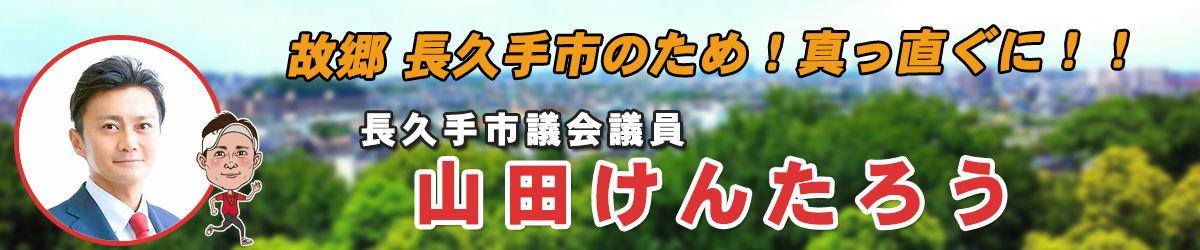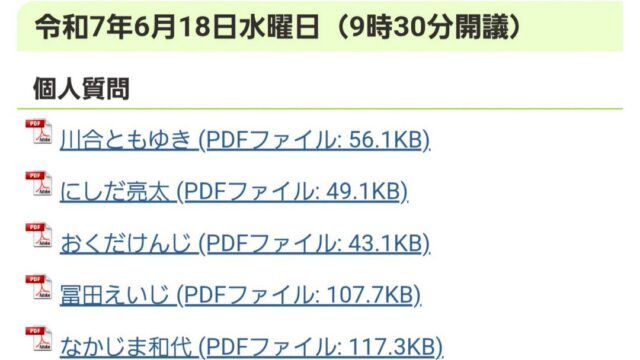港区のポートメッセなごやで開催されていた、感染症対策総合展を後にしたあと、
たまたま、
20年前、ゼネコンに勤め、施工管理職をしていた当時、
担当させて頂いた名古屋市内の現場の近くを通りました。
朝から晩まで施工管理に明け暮れ、寝るだけの家と現場の行き来をするだけの約半年間でしたが、苦楽いろいろな思い出が残ります。
強烈に記憶に残るのはまさに20年前の9月11日、降り続く雨のため、現場は早く閉め、
現場事務所内で、今後の工程の組み替えや協力業者さんとの連絡、施工図面をおこすなどの残業をして20時を迎えた頃、あまりにひどい雨音に事務所の扉を開けると、すでに外は池?川?のようになり、足を踏み出すと膝まで水が来ていました。
当時は現場にはテレビもラジオもなく、会社から安否確認の連絡もなく、事態にまったく気がつきませんでした。
同僚の社員共々慌てて帰宅することに。
私が会社から与えられていた社用車は、昭和56年式のマニュアルの軽トラでした。
いつもは30分ほどで帰宅する道を、軽トラのもつ能力をすべて使いきるつもりでギアやタイヤのスピンなどフル活用したり、
車内に入ってくる水をかわしながら川になった道を登り下りで数々のサバイバルを経験し、約5時間をかけて帰宅すると長久手市は平和そのものでした。
ほとんど寝ずで迎えた翌日、現場が心配で早出をして名古屋市内へ向かうと、名古屋市南部の現場に近づくにつれ、車がひっくりかえっていたり、泥だらけの車が乗り捨ててあったりと、異常事態であることを理解しました。
現場付近では、ところどころで道が川や海なっており、なかなか現場に近づくことができませんでしたが、なんとかたどり着き、池と化した現場をなんとかしようと、水中ポンプを手配するも、機材レンタルの事業所が水没。
うちが水中ポンプが要るんですと担当者が泣いていました。
そんなことを思い出しながら、いまも、時おり雷が鳴り、強い雨が、降ったり止んだりを繰り返しています。
災害はいつどこでも起きる可能性がある。
この経験や記憶を風化させないこと。
ハザードマップの確認をすること。
地名や土地の歴史から学ぶことがとても大切だと思いました。